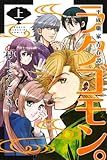あんまりまとまってない。
落語って、楽しいんですよ〜〜!(クッキングパパ風)
ということで、講談社から今月発売になった「ラクゴモン」と「こたつやみかん」の話をしましょう。
高校生、落語、という点は同じですが、「ラクゴモン」はプロ志向、「こたつやみかん」はアマ志向かな。
カバー下はどちらも必見。
落語をやる部活・サークルが、何故「落語部」ではなく「落語研究会」って名前なのかというのには諸説あり、明治時代に遡りそういう名前のプロの落語会があったからだとか、落語部ではカッコがつかなかったからだとか、よくわかりません。
また、何故か略称では「らくけん」ではなく「おちけん」と読むことになっています。
高校の部活動での落研漫画というと、漫画アクションで連載された、川島よしお「おちけん」 がある。
がある。
それより古いのとなるとすなこ育子の「お笑いを一席!」(これは中学)とか。

プロの落語家以外が落語を演じるってのは、そりゃもう昔からある。
役者やら小説家やらのエピソードとして「落語を覚えて、教室でやって見せて笑わせた」なんてのが散見される。
学生じゃあなくて素人がってのを表す「天狗連」って言葉もあるくらい。(ただし、これは落語に限らず、浪曲、講談、長唄、手品なども含む)
「こたつやみかん」は、その演じる側の楽しさってのを押して来てる。
中学、高校、大学、どこから始めるかってので差はありそう。
柳家喬太郎の新作落語では、落研をネタにした作品もあったりします。

こちらは3冊で定式幕だったけど、「ラクゴモン」は背表紙で定式幕カラー。

講談社の漫画と落語の関わりは、「のらくろ」からって言っていいのか。
そもそも社名が講談速記本から来てるのだし、演芸とは深い仲か。
週刊少年マガジンでの落語ネタ作品は、川崎のぼる「百笑亭イモ助」(1973年5月)があって、村上よしゆきはそっちつながりもあったんですね。

落語は「誰でも出来るけど奥が深い」というのがある。
- 完成されたネタ
- 漫才との差
- わかりやすさ
- そっからの深さ
寄席に行くシーンでは、やはり新宿末広亭がわかりやすい外見。
定席は東京に四つ、大阪に一つ。
探せば近くでやってるところは結構ある。
最初に見せるなら、素人芸よりもDVDでいいからプロのがいいのかなあ。
いや、親近感なら「知ってる人がやってる」というのが重要かも。
まとまらないまま、今回はここまで。